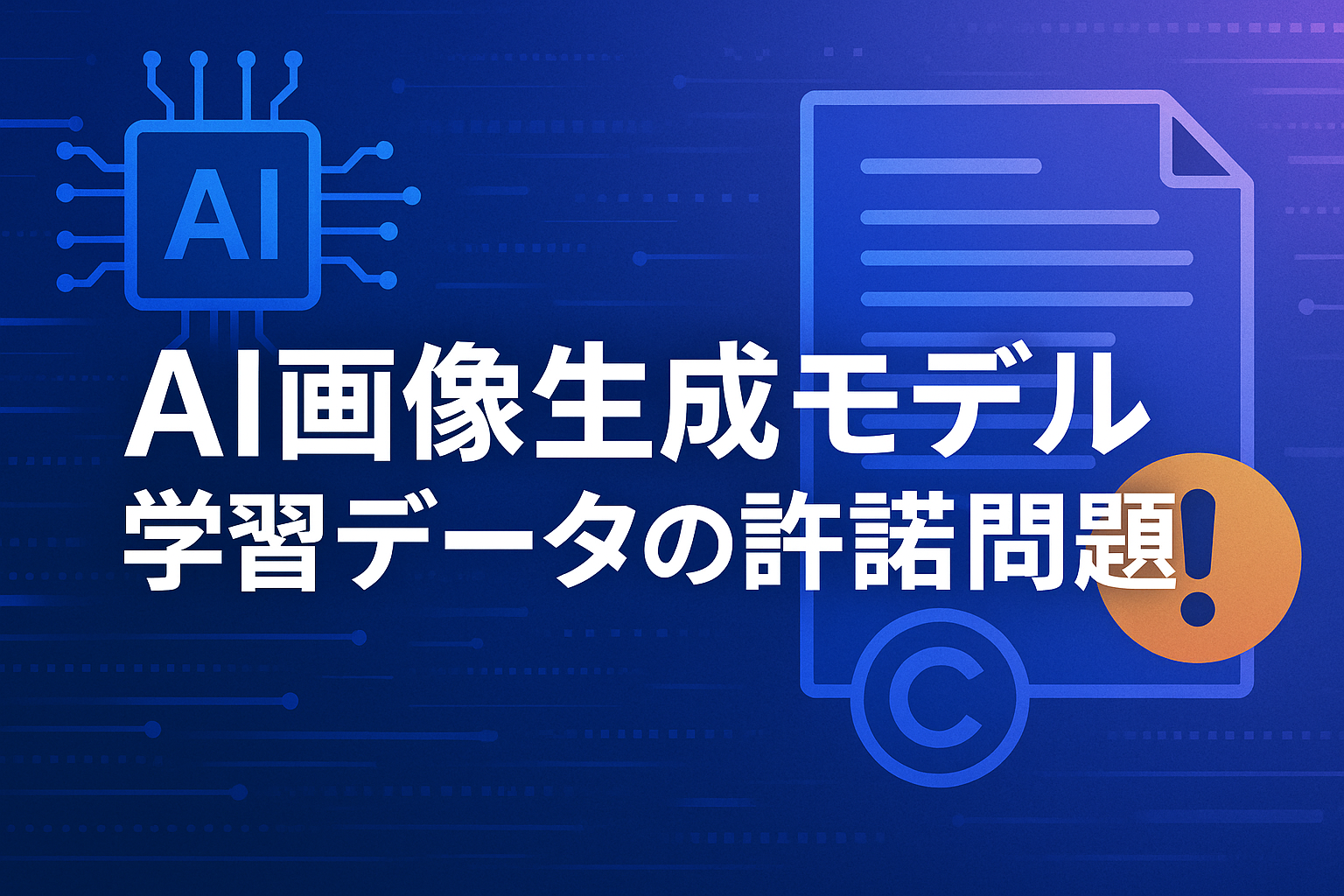AI技術の発展により、MidjourneyやStable Diffusion、DALL·E、Adobe Fireflyといった画像生成AIツールが一般に浸透してきました。高品質な画像を簡単に作れる一方で、著作権をはじめとする権利の問題が大きな話題となっています。この記事では、AI画像生成の権利問題について、最新動向を踏まえつつ網羅的に解説します。初期モデルの学習データ問題から、日本の法的枠組みやガイドライン、商用利用時の注意点、そしてフリー素材サイトでの利用ポイントまで詳しく紹介します。
初期の画像生成AIモデルと著作権問題の背景
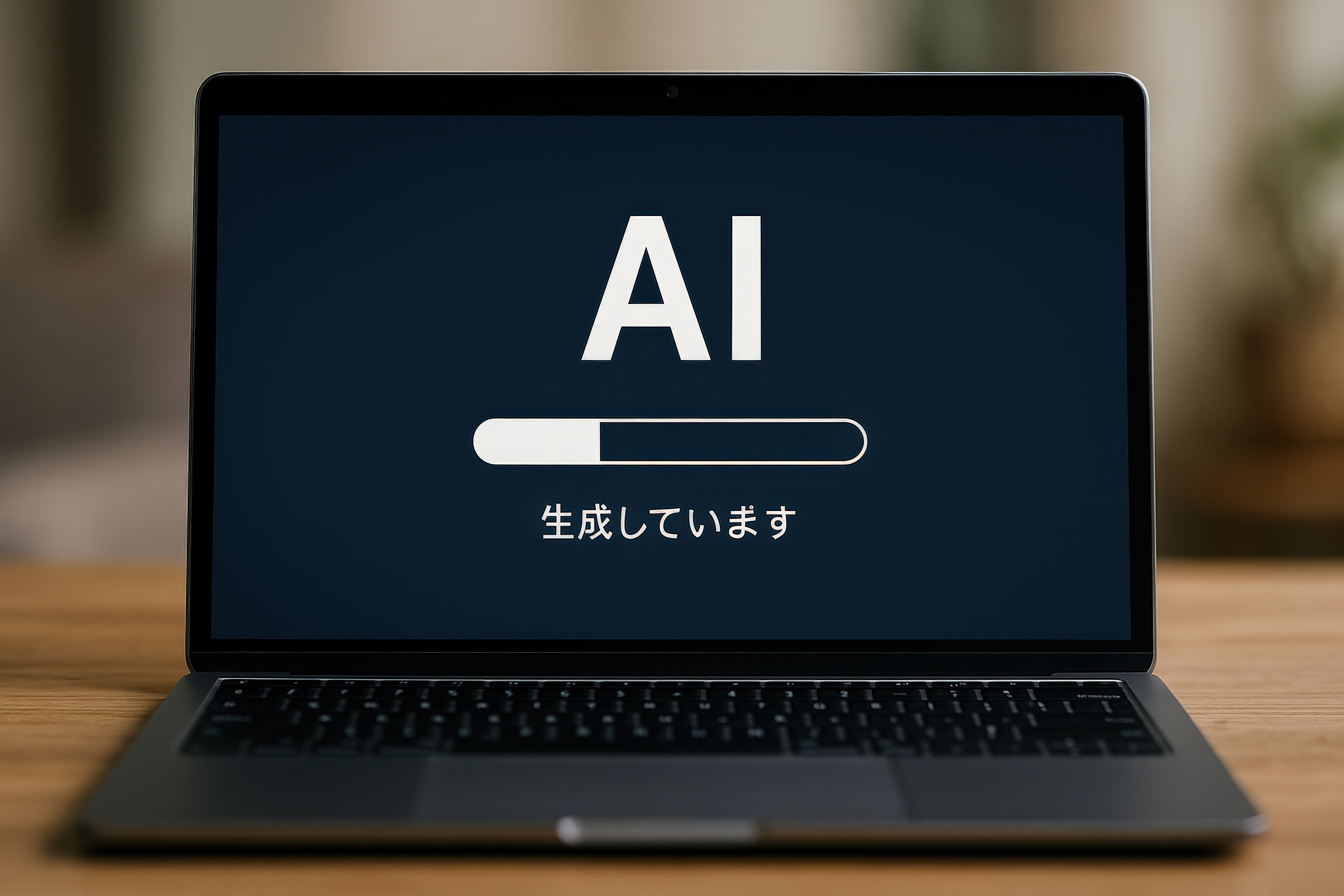
画像生成AIモデルの黎明期には、学習データに著作権者の許諾を得ていない画像が含まれていた可能性が指摘されています。多くのモデルはインターネット上の膨大な画像を収集・学習することで性能を向上させましたが、その中には著作権で保護された画像も多数含まれていたと考えられます。例えば、オープンソースのStable DiffusionはLAIONというデータセットを用いて学習しましたが、この中にはイラストレーターや写真家の作品が無断で含まれていたとして議論を呼びました。
実際に海外では、こうした無断利用に対する法的措置も始まっています。著名な例として、Getty Images社は2023年にStable Diffusionの開発元であるStability AIを提訴しました。Getty Imagesによると、Stability AIはゲッティが保有する写真を1,200万枚以上も許可なくコピーして学習に利用し、自社の競合ビジネスを構築したとされています。さらに、学習データ中のGetty画像から透かし(ウォーターマーク)が残ったような生成結果も報告されており、著作権管理情報の削除や商標侵害も問題視されています。また、アメリカではイラストレーターらがStability AIやMidjourney、DeviantArtなどを相手取り、数十億枚の画像が無断で学習に使われたとして集団訴訟を起こしています。訴状では「AIモデルの訓練に著作権保護された画像が許可なく利用された」と主張されており、AI開発企業による大量の無断コピーにクリエイター側が反発している状況です。
中国では「ウルトラマン」などの特撮ヒーロー画像を無断学習したとして、円谷プロダクションがMidjourneyを提訴するケースも起きました。この訴訟では、Midjourneyが許可なくウルトラマンの画像を学習データに取り込み、酷似した画像を生成・配布したことが問題となり、中国の裁判所は円谷プロ側の主張を認め賠償命令を下しています。こうした事例は、初期の生成AIモデルが直面した著作権リスクを象徴しています。
権利未許諾データ問題の詳細

なぜ初期の画像生成AIモデルでこのような権利問題が生じたのでしょうか。その背景には、AIを高精度に動かすために大量の既存画像データが必要であったことがあります。2010年代後半から2020年代前半に登場したモデルの多くは、インターネット上の画像(写真、イラスト、美術作品など)を網羅的に収集・解析することで「学習」してきました。しかし、この学習用データ収集は著作権者から明示の許諾を得ずに行われるケースがほとんどでした。その結果、オリジナルのクリエイターの権利を侵害しているのではないかという懸念が生じたのです。
特に画像生成AIが生成する作品が、元の作品に似すぎている場合には問題が顕在化します。たとえばStable Diffusionから出力された画像にGetty Imagesの透かしが微かに残っていた事例では、元画像を無断使用した証左として批判されました。また、Midjourneyなどで特定のアーティストの名前をプロンプトに入力すると、そのアーティストの作風を真似た画像が出てくることがありますが、これも**「著作者人格権」や**著作権侵害の可能性が指摘されています。既存の著作物に酷似した画像を生成すれば、著作権侵害に該当すると見なされ訴訟リスクがあると専門家も警鐘を鳴らしています。
このように、初期モデルの学習データ問題は「AIによる分析・学習行為」が著作権法上適法か否かという根本的な論点と、「生成物が既存作品に似ている場合に侵害となるか」という応用的な論点の両面から議論されています。
権利クリアなデータセットへのシフト:Adobe Fireflyなど新世代AIツール

こうした著作権リスクへの懸念が高まる中、AI開発企業側でも対応の動きが出てきました。最近の生成AIツールでは、学習に使用する素材を厳選し、権利処理済みの画像のみを使う方針が取られ始めています。代表例がAdobe社の「Firefly」です。Adobe Fireflyは、学習データとしてAdobe Stockの提供画像やオープンライセンスのコンテンツ、そして著作権が切れたパブリックドメイン素材のみを活用してモデルを訓練しています。つまり、権利関係がクリアな画像だけで学習させているため、著作権侵害と商用利用の問題をクリアにしているのです。この結果、Fireflyが生成する画像はビジネス目的でも安心して利用可能とされています。
Adobe以外にも、ストックフォト大手のShutterstockはOpenAIと提携して、自社のライセンス済み画像を活用したAI画像生成サービスを開始しました。また、Getty Imagesも自社保有の膨大な画像資産を元にした生成AIツールの開発を進めています。
このように、新世代の画像生成AIでは「学習段階で著作権を侵害しない」ことを重視した設計が進んでいます。権利処理済みデータへのシフトは、クリエイターや権利者との軋轢を減らし、生成AIの商用利用ハードルを下げる効果があります。ユーザーにとっても、出力された画像を安心してビジネス利用できるメリットが大きいでしょう。
日本における法的枠組みとガイドライン
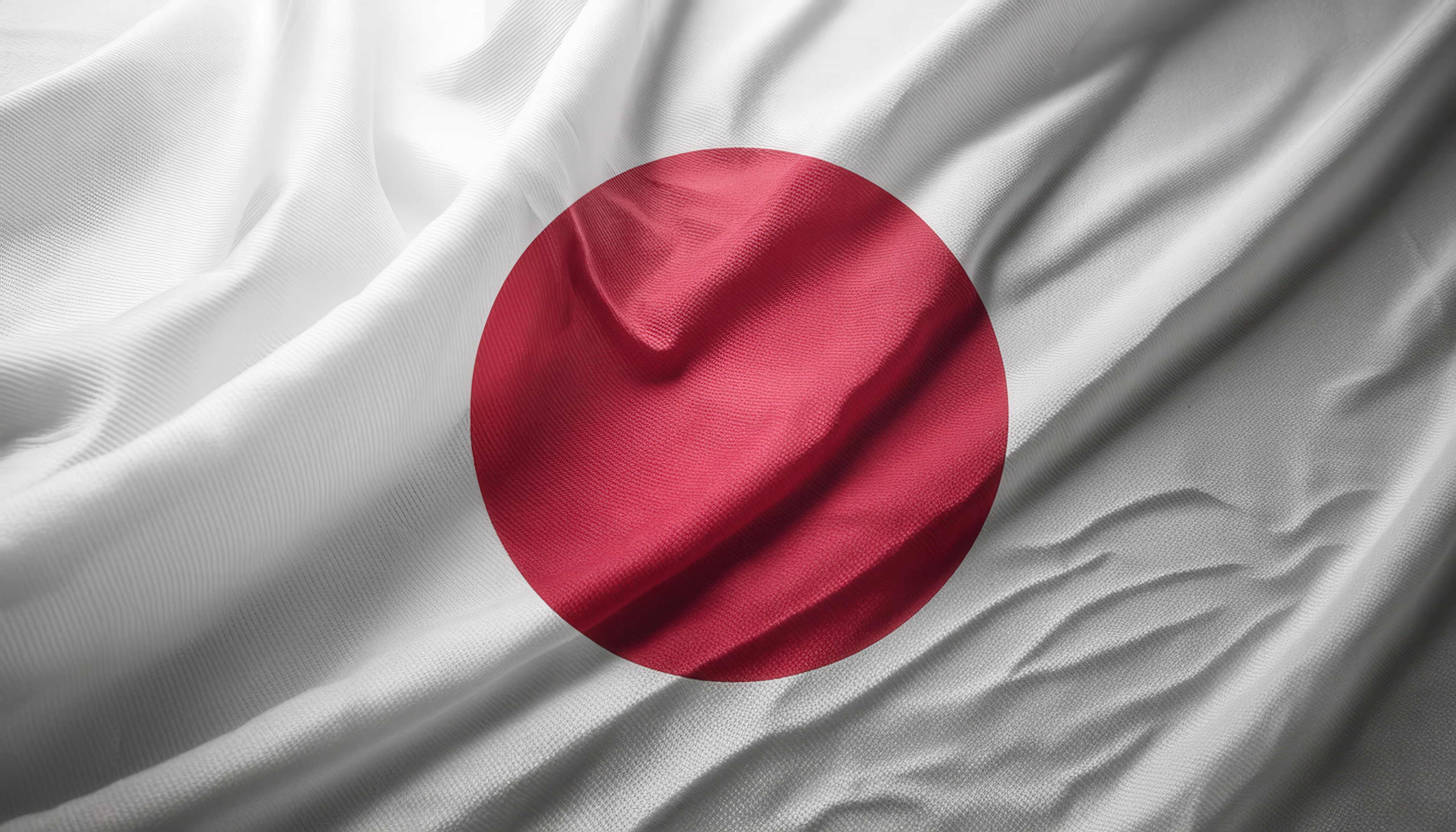
日本の著作権法は、AIの学習行為や生成物に関する問題にどう対応しているのでしょうか。結論から言えば、現行法にはAIに特化した明示的な規定はないものの、関連する条文や政府見解により一定の指針が示されています。
まず、AIの開発・学習段階について日本の著作権法は「情報解析(データ解析)のための複製」に関する規定(著作権法第30条の4)を設けています。この規定は、簡単に言えば「鑑賞や視聴といった享受を目的としない分析のためであれば、権利者の許諾なく著作物を利用できる」というものです。
AIの学習行為は、人間が直接作品を鑑賞するわけではなく、データとして解析する行為なので、この第30条の4の適用対象になると解釈されています。実際、文化庁の見解でも「AIの学習における著作物の利用は原則として許諾不要」と明言されています。つまり、日本では既存の著作物をAIに学習させること自体は違法ではないとの立場が示されているのです。
ただし、この「許諾不要」は無制限に認められるわけではありません。文化庁は続けて「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」とも述べており、一定の歯止めを設けています。
たとえば、AIの学習結果として原著作物と実質的に同一なコンテンツを再現できてしまう場合や、権利者の市場を代替してしまう場合は「権利者の利益を不当に害する」ケースに該当し得ます。このような場合には例外規定の適用が外れ、著作権侵害と判断される可能性**がある点に注意が必要です。
もっとも、現在のところ日本国内でこうしたケースが具体的に裁判で争われた例は少なく、最終的な解釈は今後の判例の蓄積に委ねられている部分もあります。文化庁も「今後もAIの発展・普及に応じて考え方を整理し、必要に応じ見直す」としており、引き続き議論を深める姿勢を示しています。
以上のような状況を踏まえ、日本政府もガイドライン整備を進めています。文化審議会の著作権分科会法制度小委員会は2024年3月、「AIと著作権に関する考え方」という文書を取りまとめ、公表しました。
この中で、先述の学習段階(第30条の4の解釈)と生成・利用段階(生成物の著作物性判断)に分けて現行法の適用考え方を整理しています。
また、経済産業省・総務省も2024年4月に「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を公開し、AIサービス提供者が遵守すべき知的財産やデータ取扱い上の指針を示しています。さらに経産省はコンテンツ産業向けに「生成AI利活用ガイドブック」を作成し、ゲーム・アニメ・広告分野でAIを活用する際の法的留意点を解説しています。
これらガイドラインは法的拘束力こそありませんが、企業やユーザーがAIを利用する際の実務的な指針となるものです。特に著作権については、先述の文化庁の考え方と整合的に、権利者に無断で第三者のコンテンツを学習・生成物利用しないことや、生成物に他人の権利を侵害し得る要素が含まれないか注意することなどが強調されています。
AI生成画像の商用利用は可能か?注意すべきポイント

では、生成AIで作られた画像をビジネス用途(商用利用)しても良いのでしょうか。この問いに対する答えは「基本的には利用可能だが、いくつか注意点がある」です。
まず、主要な画像生成AIサービスの利用規約を見てみると、Midjourney、Stable Diffusion、DALL·E 2、Adobe Fireflyといった多くのサービスで生成画像の商用利用が認められています。
例えばMidjourneyの場合、有料プランを利用すれば生成画像の権利は利用者に与えられ、自由に商用利用することが可能です(※無料プランでは生成物が公開されるため権利主張できない制限があります)。実際、Midjourneyの公式見解でも「生成画像に著作権はなく商用利用可能」とされています。同様に、OpenAIのDALL·E 2も利用者が出力画像を商用含め好きに使うことを許諾していますし、Stable Diffusionはオープンソースゆえ制限なく利用できます。Adobe Fireflyも前述のように権利処理済みデータで学習しているため生成画像を商用プロジェクトに安心して使えると案内しています。
しかし、「商用利用できる=何をしても安全」というわけではありません。商用利用時に特に注意すべきポイントを以下に挙げます。
- 利用規約の順守: 各サービスの規約で定められた条件を守る必要があります。例えばMidjourneyは年間収益が一定額を超える企業には上位プラン契約を求めていますし、禁止事項として他人を誹謗中傷する用途や違法用途での利用を禁じています。サービスごとに細かな規定があるため、事前に利用規約をよく確認しましょう。
- 生成画像の内容チェック: 生成された画像に第三者の権利を侵害する要素が含まれていないかを厳重に確認する必要があります。具体的には、有名キャラクターや著名人の肖像などが含まれていないかチェックしましょう。AIの出力次第では、意図せずとも既存のキャラクターに酷似したデザインや、市販の商品とそっくりな画像が生成されてしまうことがあります。そのような画像を商用利用すると、著作権だけでなく商標権や肖像権(パブリシティ権)の侵害を問われるリスクがあります。既存の著作物に類似したコンテンツを生成・使用すれば訴訟リスクが生じることは先述の事例が示す通りです。商用利用する画像は、公開前に第三者の権利侵害のおそれがないか入念に確認しましょう。
- 著作権表示やクレジット: AIが生成した画像には原則として著作権がありませんが、サービスによっては利用時にクレジット表記(例:「Image generated by Midjourney」など)を推奨または要求している場合があります。必須ではなくても、出所を明示することは透明性の観点から望ましいでしょう。また、共同制作者がいる場合(AIで生成した素材を人間が加工したなど)は、その関与に応じて適切にクレジットを付与することも検討してください。
- 独自性の付与: AI生成画像は他のユーザーも同じプロンプトを入力すれば似たものを得られる可能性があります。また著作物性が認められない場合、法的には誰でも二次利用できてしまう状態です。ビジネスで差別化を図りたいなら、AI生成画像をそのまま使うだけでなく、自社のデザイン要素を加えるなど独自性を持たせる工夫が有効です。例えば、AIが作成したイラストを一部加工してブランドのテイストを反映させる、複数のAI画像や写真素材を合成して新たなビジュアルを作る、といった方法です。こうすることで、万一後から類似のAI画像が出回っても自社コンテンツとの差別化を保ちやすくなります。
要するに、AI画像の商用利用自体は各サービスで許諾されつつあるものの、利用者側のリテラシーと注意深さが求められるということです。実務上は「自社でその画像を使うことによるリスクはないか?」を常に検討し、問題があれば別の画像に差し替えるなど柔軟に対応できる姿勢が大切です。
フリー素材サイトで配布されるAI画像の利用ポイント

最近では、フリー素材サイトにもAI画像生成ツールで作成された素材が多数登録されるようになりました。「無料で使えるなら」とダウンロードを検討するユーザーも多いでしょう。ここでは、フリー素材サイト上のAI生成画像を利用する際のポイントや注意点を解説します。
まず大前提として、信頼できるフリー素材サイトに掲載されている画像であれば、基本的には商用利用可能です。多くの素材サイトでは、掲載画像に対して「パブリックドメイン相当」「CC0」あるいはサイト独自の無料利用ライセンスを付与しており、クレジット表記不要で商用利用OKとなっています。AI生成画像についても、人間の撮影や作画による画像と同様の扱いで提供されているケースがほとんどです。ただし、サイトの規約によって細かな条件が異なるため、利用前に利用許諾範囲を確認することをおすすめします。
特に確認すべきは、有名時に似た人物が写っている場合です。一般にフリー素材サイトの免責事項として「画像に写り込んだ商標・ブランド・人物等についてまで権利保証していない」という旨が記載されています。AI画像の場合、実在の人物の写真は通常含まれませんが、リアルな人物風のAIイラストなどは注意が必要です。それが架空の人物であれば問題ありませんが、万一特定の有名人に酷似してしまった場合や、本人そっくりの肖像を生成していた場合にはトラブルになりかねません。ダウンロードしたAI画像に不審な要素がないか、商用利用前に一度チェックすると安心です。
幸い、近年の大手フリー素材サイトはAI素材に関するポリシー整備も進めています。ユーザー投稿型のサイトでもAI生成画像であることを明示するタグを設けたり、品質管理チームが明らかに既存キャラクターそっくりの画像を除外するなど、トラブルを未然に防ぐ工夫をしています。利用者側も、サイト上で「この素材はAIによって生成されました」等の注意書きを見かけたら、その意味を理解した上で使うと良いでしょう(例:「AI生成画像なので著作権は存在しないが、類似画像が他にも生成され得る」といった点を念頭に置く)。
もう一点、フリー素材サイトの利用規約上の禁止事項にも留意が必要です。多くのサイトでは、「素材を再配布・転売しないこと」「公序良俗に反する用途に使わないこと」などが定められています。AI画像であってもこれは同じで、ダウンロードした無料素材をそのまま自社の素材集として再提供するような行為は厳禁です。
総じて、フリー素材サイトでAI生成画像を利用すること自体に大きな問題はありません。サイト運営者側でも、安心して使える素材を提供すべく権利処理やガイドライン整備が進んでいます。ユーザーとしては、サイトの利用規約を守りつつ、画像内容のチェックを怠らないことさえ心がければ、AI画像を便利なフリー素材として十分活用できるでしょう。
最後に
AI画像生成技術と法制度・社会ルールは今なお発展途上にあります。2025年現在の状況では各種ガイドラインが示され一定の方向性が見えつつありますが、新たな判例や国際的な動きによって解釈が変化する可能性もあります。読者の皆さんには、最新情報にアンテナを張りながら、創造性と法的リスクのバランスを取りつつAI画像を活用することをおすすめします。適切な知識と意識を持っていれば、AI画像生成ツールは強力な味方となり、クリエイティブの可能性を大いに広げてくれるでしょう。
【参考資料】
- 文化庁 著作権課 「AIと著作権に関する考え方について」 (令和6年3月15日)newton-consulting.co.jpnewton-consulting.co.jp
- 経済産業省・総務省 「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(2024年4月)meti.go.jp
- IPmag 「Midjourneyの著作権の扱いと商用利用の条件」ipmag.skettt.comipmag.skettt.com
- Power Interactive 「生成AI活用と著作権侵害のリスク」powerweb.co.jppowerweb.co.jp
- Getty Images vs. Stability AI 訴訟報道pc.watch.impress.co.jp